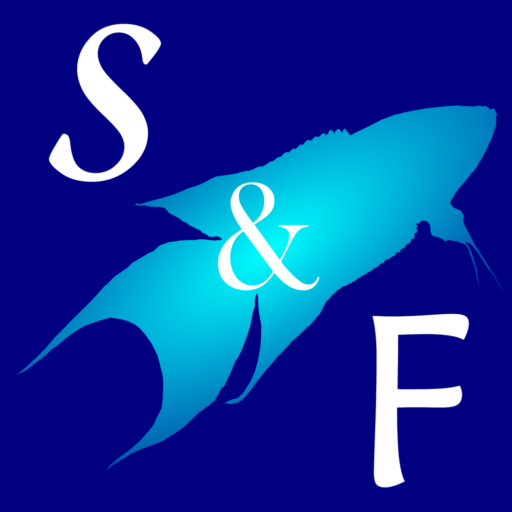春はメダカ飼育にとって、その後1年を左右する大切な季節です。
冬眠で体力が落ちたメダカを上手く本調子にさせることで、スムーズに飼育や繁殖につなげることができます。
ただし、水温やメダカの調子が変わりやすい季節なので、水換えや掃除、餌やりは「春ならではの方法」で行うことが重要です。
今回は、春のメダカ飼育に必要なコツ5選を紹介します。

目次
春のメダカ飼育では水温・水換え・餌やりに気を付ける!

春のメダカ飼育では「水温」と「水換え」、「餌やり」この3つが大きなポイントです。
水温が上がればメダカの代謝も上がり、よく活動したり、餌を食べたりしますが、春(3~5月)は水温が変わりやすいので代謝もコロコロ変わりがちです。
また、冬眠明けは長期間の低水温と餌を食べていないことが原因で体力が落ちています。
その状態で水換えをすると、水質や水温の変化に耐えられず死んでしまうことも珍しくありません。
水換えのタイミングと一度に換える水量は、活性が高い季節よりも気を付ける必要があります。
春のメダカ飼育に必要なコツ5選!水換え・掃除・餌のやり方

春のメダカ飼育に必要なコツは次の5つです。
- 世話をする前に水温を確認する
- 餌やりは水温が上がったときだけ
- 多量の水換えや大掃除はしない
- 本格的に繁殖させるのは5月から
- メダカの天敵対策をする
水温と水換えはもちろん、繁殖や天敵についても春ならではのコツがあります。どれも難しいことではなく、意識するだけですぐ実践できるものばかりです。
簡単でも大切なことなので、一つひとつ具体的に解説していきますね。

世話をする前に水温を確認する!

餌をやったり、水換えをしたりなど世話をするときは「水温」を確認しましょう。
メダカの様子を見ただけで体調がわかれば良いのですが、そう簡単にはいきません。そのようなときに水温が世話をするかどうかの指標になります。
0~10℃→餌やり・水換えをしない
15℃前後→少量の餌やり・水換えをしても良い
20℃以上→餌やり・水換えをしても問題なし
水温が低い場合は冬眠しているので、世話しなくても大丈夫です。春でも3月頃は冷え込むことが珍しくありません。
15℃前後になると、メダカの代謝が上がり活動を始めるため世話をします。

4月の暖かい日や5月になれば水温が20℃を超えてメダカが活発に泳ぎ回るので、本格的に世話をしても問題ありません。
餌やりは水温が上がったときだけ

水温が低く代謝が落ちているときに餌をやってしまうと、消化不良につながり体調をくずしてしまうこともあるので、餌は水温が上がったときだけ与えましょう。
水温の変化が激しい3~4月は特に注意が必要ですが、5月になって水温が安定すれば問題ありません。
水温の変化やメダカの調子に合わせた餌やりの方法はこちらの記事で解説しています。
多量の水換えや大掃除はしない

春のメダカ飼育では、多量の水換えや大掃除はしないほうが良いです。

3月前半は気を付けたほうが良いですが4月にもなれば体力も回復しているため、通常の飼育方法で大丈夫です。
本格的に繁殖させるのは5月から

春はメダカが繁殖を始める季節です。
ただ本格的に繁殖させるのは後半の5月に入ってからにしましょう。それは、「水温」が関係しています。
3~4月は水温が安定せず上がらない日も多々あるため、孵化に時間がかかってしまうことも珍しくありません。すると卵にカビが生えやすくなり孵化率が下がってしまいます。

経験としては、3月半ばから後半にかけて産卵を始めることが多いです。
この時期に孵化率を上げたい場合は、水槽用ヒーターで加温する必要があります。
できないこともありませんが手間ですし3~4月はメダカの調子を万全に整える期間にして、5月に入ってから本格的に繁殖に挑戦することをおすすめします。
メダカの繁殖や孵化率を上げる方法は、こちらの記事で詳しく解説しています。
メダカの天敵対策をする

春はメダカを食べてしまう天敵も活動を始めます。
「寒いからまだ大丈夫!」
そう油断していると、冬眠明けで動きの鈍いメダカが食べられてしまうことも。
次の生き物はメダカを食べてしまうことがあるので注意してください。
- 昆虫類:ヤゴ、マツモムシ、コオイムシ、ゲンゴロウなど
- 両生類:トノサマガエル、ツチガエル、ウシガエルなど
- 鳥類:カラス、サギ、カワセミ、ヤマセミ、シジュウカラ、セキレイなど
- 哺乳類:アライグマ、イタチ、ハクビシンなど
飼育容器に入ってしまったものは取り出すしかないので、入らないようにすることが重要です。
園芸用のネットや金網を被せる方法が簡単でおすすめ。


余談ですが近年では人による盗難も目立ちます。目を付けられやすい高価なメダカを飼育している場合は、監視カメラの導入も検討してみてください。
メダカの天敵対策は、こちらの記事をご覧ください。
まとめ:春のメダカ飼育に必要なコツ5選!冬眠明けは水温・水換え・餌やりに注意

春のメダカ飼育では水温が世話をする指標になり、水換えが体調を左右します。
この2つを念頭に置きながら、
- 世話をする前に水温を確認する
- 餌やりは水温が上がったときだけ
- 多量の水換えや大掃除はしない
- 本格的に繁殖させるのは5月から
- メダカの天敵対策をする
この5つのコツを心がけてみてください。
春から夏に向けてメダカ飼育の良いスタートが切れるようになります。